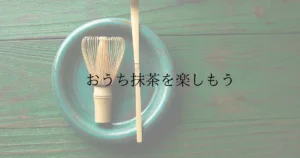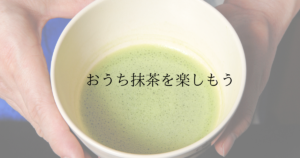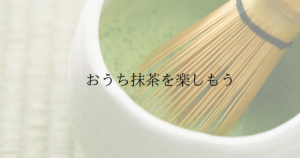誰がために茶を点てる

今日はテーブル茶道や茶道の哲学を少し。
目次
お茶を点てるのは誰のためなのでしょう?
お客さんがいるのか自服でいただく(自分で点てたものを自分で飲む)のかに関わらず、
お茶を点てるのは究極的には自分自身のためと考えます。
※ここからは伝統的な茶道とテーブル茶道の区別なく、「茶道」と表記します。
茶道の時間は自分と対話する静かな時間
茶道の世界に入ると、しんと静まった凛とした時間が流れます。
また、言葉を介さないコミュニケーション(お軸やお花、お道具やお茶菓子の取り合わせから伝わる亭主のおもてなし)があるため、お茶室の中やお点前の様々なところに意識を向けるようになります。
まさに今、この瞬間に意識を向けるマインドフルネスの時間になるのです。
これは自分がもてなす側になった際も同じです。
お点前やおもてなしをするには、集中力が欠かせません。
お点前中は基本的に言葉を発することはありませんので、
ただ一服のお茶を点てることに集中するのみです。
茶道は五感で味わう上質な時間
お道具や茶室の設え(お花やお軸)を質感や色を見て触って選び
お抹茶とお茶菓子の色や香りを感じて味わいを楽しみ
お点前を目で見て音で聴いて香りを嗅いで…
と五感をフル活用することになります。
もちろんもてなす相手がいる場合は相手のことを考えて準備をするわけですが、自服でいただく場合も(一部の設えを省略するにしても)、自分が少しでも気分が上がるようなお茶菓子やお茶碗、お道具を選びませんか?
つまり自服の場合も「自分で自分を」もてなしているわけです。
3月の禅語 | 百花為誰開 (ひゃっか たがためにひらく)
春に咲く花は誰のために咲くのか?という問いを表した禅語です。
実際は「誰かのために」咲くのではなく、
花が持って生まれた「咲くという役割」をただ果たしているだけなのです。
そこに利己的なものは一切ありませんから、役割を果たす花自身のためとも言えるでしょう。